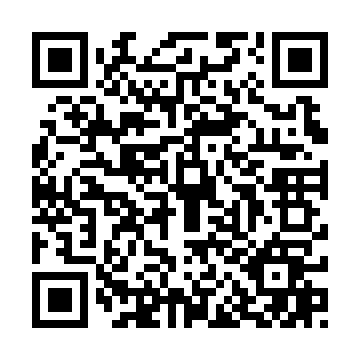当社は内部体制見直しのため、第二種金融商品取引業および投資助言・代理業の業務を中止しております。
新着ニュース
フォーサイトビジネスジャパン株式会社(FBJ)は、金融商品取引業務のうち、第二種金融商品取引業、及び投資助言・代理業の取り扱いを行っております。
当社では、第二種金融商品取引業社として事業者様が展開されるビジネスにおける資金調達方法や、適した事業構成、円滑な業務の遂行などの総合的なコンサルティングから、実際のビジネスを実現させるための円滑な資金調達のお手伝いさせていただきます。日本経済への貢献を目的とし、その使命を幅広く堅実に実現するため自由な発想力と、高い使命感、倫理観を持って、誠実に業務を営む所存です。
また、投資助言・代理業として、個人投資家様・法人投資家様へ、投資初心者からベテランまで幅広い層の方々に、当社独自の『相場分析システム』を通じて、投資助言をさせていただきます。さらなる研究開発と分析を重ね、良質なサービスを提供できるよう努力していく所存です。
お客様から大いなるご信頼を伴う良きパートナーとしてご愛顧いただけますよう、お客様の利益につながる金融商品取引業者としての役目を果たすべく、社員一同、力を尽くして参りますので、何卒、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申しあげます。